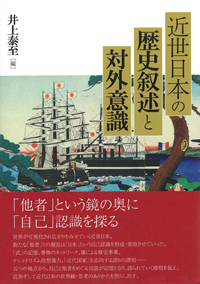日韓近期漢學出版物(十八)
32、近世日本の歴史敘述と対外意識
時 間:2016年6月
作 者:井上泰至 編
出版單位:東京:勉誠出版
內容簡介:
序―自分らしさという「確信」はどこから生まれるのか?(井上泰至)
第一部 「武」の記憶のナルシシズム
朝鮮観の変転―近世の歴史敘述と対外認識を論ずるために(井上泰至)
寫本軍書類に見る朝鮮出兵時の立花宗茂と小早川隆景―語り継がれる「碧蹄館の戦い」の記憶(倉員正江)
フヴォストフ事件と『北海異談』―壬辰戦爭の戦爭史的な検討と『海國兵談』の利用を中心に(金時徳)
硫黃島の安徳天皇伝承と薩摩藩·島津斉興―文政十年の「寶鏡」召し上げをめぐって(鈴木彰)
第二部 書物のネットワークが生み出す世界観
室鳩巣『赤穂義人録』論―その微意と対外意識(川平敏文)
〈異國襲來〉の原像―塙保己一『螢蠅抄』から(佐伯真一)
節用集の付録による教養形成研究のための覚書(佐藤貴裕)
長崎通詞の西歐文明理解―志筑忠雄を手掛かりに(久保誠)
第三部 藩という武家「國家」の修史事業
松浦靜山のみた境界と「屬地」―普陀山をめぐる考證から(吉村雅美)
大名文庫形成試論―大名はなぜ古典籍を集めたのか(前田雅之)
『大日本史贊藪』所収外國伝贊の対外史認識(勢田道生)
島津家の歴史編纂と幕末薩摩藩の対外意識(寺尾美保)
第四部 ナショナリズム的想象力の誤読
國學者の歴史認識と対外意識―本居宣長『馭戎慨言』をめぐって(田中康二)
『日本外史』の執筆意図と誤読(濱野靖一郎)
「鎖國論」から「異人恐怖伝」へ(大島明秀)
『萬國公法』と「皇國」の「公法」(三ツ松誠)
第五部 近代日本國家の言說の諸相へ
近世の考證的學問から近代國學へ(藤田大誠)
一八七四年の「臺灣危機」―「回避した戦爭」をめぐる諸言說について(樋口大佑)
時代と世話の「朝鮮事変」―河竹黙阿彌は壬午事変をどう描いたか(日置貴之)
近世漢詩に描かれた壬辰戦爭(合山林太郎)
軍神を生み出す回路―幕末の楠正成(井上泰至)
33、近代中國研究と市古宙三
時 間:2016年6月
作 者:東洋文庫近代中國研究班 編
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
「戦后中國近代史研究と東洋文庫──市古先生のお仕事を偲ぶ」
戦后中國近代史研究と東洋文庫(久保田文次)
學生としてみた市古先生(浜口允子)
外國人研究者として見た市古先生(リンダ·グローブ)
市古先生とAF問題(石島紀之)
市古宙三先生と近代中國研究─中央大學との關わり(土田哲夫)
文庫の中からの市古先生(鶴見尚弘)
(附)報告レジュメ(久保田文次,土田哲夫)
戦后中國近代史研究における東洋文庫と中央研究院近代史研究所の果たした役割について(林明徳)
34、消え去る差異、生み出される差異:中國水上居民のエスニシティ
時 間:2016年6月
作 者:稲澤努 著
出版單位:仙臺:東北大學出版會
內容簡介:
序章 問題の所在
第1章 水上居民像の形成
第2章 水上居民像の再編
第3章 調査地概況——広東における汕尾
第4章 汕尾における「漁村」の成立
第5章 「漁村』の廟活動と漁民像の資源化ー漁村理事會の活動を中心に
第6章 汕尾市における諸エスニック·カテゴリーと「漁民」
第7章 あらたな他者とエスニシティ
終章 結論——消え去る差異、生み出される差異
35、開港期朝鮮の戦略的外交(1882-1884)
時 間:2016年3月
作 者:酒井裕美 著
出版單位:大阪:大阪大學出版會
內容簡介:
序論
第Ⅰ部 開港期朝鮮の外交主體·統理交渉通商事務衙門
第一章 統理交渉通商事務衙門成立前史
第二章 統理交渉通商事務衙門の構成員
第三章 統理交渉通商事務衙門の活動実態-地方官庁との關系から
第Ⅱ部 朝清宗屬關系をめぐる朝鮮外交の展開
第四章 朝清商民水陸貿易章程と關連諸章程の成立
第五章 朝清陸路貿易の改編と中江貿易章程
第六章 対清懸案事項の處理過程にみる諸章程の運用実態
第Ⅲ部 不平等條約をめぐる朝鮮外交の展開
第七章 關稅「自主」をめぐる朝鮮外交の展開-「日朝通商章程」を中心に
第八章 最恵國待遇條項をめぐる朝鮮外交の展開-朝米修好通商條約を中心に
第九章 最恵國待遇の運用をめぐる朝鮮外交の展開-朝英修好條約均沾問題を中心に
結論
資料來源:臺北《漢學研究通訊》、臺北《國家圖書館電子報》等 陳友冰輯