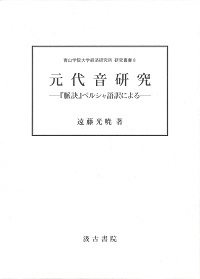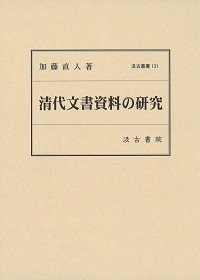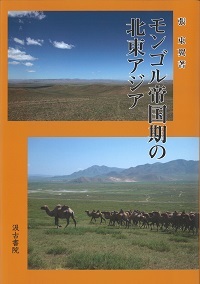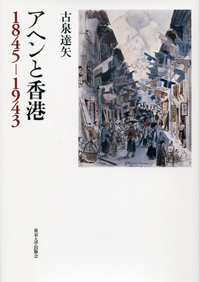日韓近期漢學出版物(十七)
9、中國古代國家と情報伝達——秦漢簡牘の研究
時 間:2016年3月
作 者:藤田勝久 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
序章 中國古代の出土數據と情報伝達
第一編 秦漢簡牘の機能と情報伝達
第一章 里耶秦簡と秦代郡県制
第二章 漢代地方の文書逓伝と情報處理
第三章 漢代地方の文書處理と「発」
〔補論〕「署某発」について
第四章 漢代檄の伝達方法と機能——文書と口頭伝達
第五章 漢代交通と伝の機能——懸泉漢簡を中心として
第六章 漢簡にみえる地方官府の伝
第二編 秦漢時代の交通と情報伝達
第七章 秦漢交通システムと出土資料
第八章 漢代西北の交通と懸泉置
第九章 エチナ河流域の交通と肩水金關
第十章 后漢時代の交通と情報伝達——褒斜道の石刻をめぐって
終章 中國古代の出土數據と地域社會
10、元代音研究——『脈訣』ペルシャ語訳
時 間:2016年3月
作 者:遠藤光曉 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
研究篇
1.序論
2.文獻學的研究
3.ペルシャ文字の転寫と音価
4.聲母の対応
5.韻母の対応
6.聲調の対応
7.話者·音訳者·書寫者の識別
8.音節総表
9.基礎方言
10.結論
資料篇
口絵(カラー8頁)/『脈訣』出現順音訳総表/『脈訣』音訳中古音順一覧表
11、三國志演義成立史の研究
時 間:2016年3月
作 者:井口千雪 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
【主要目次】
序(小松謙)
前言/凡例
序章 諸版本の體裁から見た刊行経緯と受容のあり方——武定侯郭勛刊本の位置づけ
導論篇
第一章 成立と展開——段階的成立の可能性
前篇 「原演義」から諸版本へ
第二章 三系統の版本の継承關系——簡本系版本をてがかりに
第三章 三系統の異同の全體像から見た成立過程の考察——序盤·中盤·終盤の成立時期の違い
第四章 關索說話に關する考察
后篇 「羅貫中原本」の成立と「原演義」への発展
第五章 執筆プロセスに關わる考察
第六章 『三國志演義』と『蜀漢本末』——南蠻王孟獲討伐を中心に
第七章 終盤の后補——結尾の部分を中心に
結語/初出一覧/索引
12、前漢國家構造の研究
時 間:2016年3月
作 者:楯身智志 著
出版單位:東京:早稲田大學出版部
內容簡介:
序章 先行研究の総括と問題の所在
第一章 民爵賜與の起源と変遷
第二章 功臣層の形成――劉邦集団の內部構造と「侯子」·「宦皇帝者」
第三章 高祖功臣位次考
第四章 「郡國制」の形成と展開
第五章 官吏登用制度の変遷と「官爵」の形成
第六章 劉氏淮南王國の興亡
第七章 宗正の政治的役割より見た皇帝·諸侯王關系
終章 総括と展望
附章 帝賜の構造と「爵制的秩序」
13、中國古典名劇選
時 間:2016年3月
作 者:后藤裕也、西川芳樹、林雅清 編譯
出版單位:東京:東方書店
內容簡介:
趙氏の孤児、大いに讎を報いる(紀君祥)
臨江の駅、瀟湘にふる秋夜の雨(楊顕之)
東堂の老、家破す子弟を勧す(秦簡夫)
李亜仙、花酒の曲江池(石君寶)
唐の明皇、秋夜梧桐にふる雨(白仁甫)
河南府の張鼎、頭巾を勘す(孫仲章)
邯鄲道、黃梁の夢に省悟める(馬致遠)
布袋和尚、忍の字の記(鄭廷玉)
杜蕊娘、智もて金線池を賞でる(關漢卿)
玎玎珰珰、盆児の鬼(無名氏)
14、清代文書資料の研究
時 間:2016年2月
作 者:加藤直人 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
序章 清代文書數據と満洲語
第1部 入關前清朝における文書制度の展開と「史書」の編纂
第1章 入關前清朝文書數據に關する學說史的検討
第2章 八旗値月檔と清初の記録
第3章 清初の文書記録と「逃人檔」
第2部 19世紀以降における清朝文書制度の展開——天理図書館所蔵の清朝檔案群を例として第1章 天理図書館所蔵「伊犂奏折稿檔」について
第2章 天理図書館所蔵「伊犂奏折」について
第3章 天理図書館蔵、グキン(固慶)の奏折について——とくに科布多參贊大臣時代の奏折を中心として
第3部 清朝の文書の多様性——宮中、旗人、私文書
第1章 清代起居注の研究
第2章 嘉慶帝の即位と皇后の冊立——「嘉慶元年冊封皇后貴妃妃嬪檔」の分析をとおして
第3章 清代雙城堡の屯墾について——咸豊元年の副都統職銜総管設置をめぐって
第4章 19世紀后半、オロチョン人の編旗とブトハ問題
終章 清朝文書數據の地平
15、モンゴル帝國期の北東アジア
時 間:2016年2月
作 者:張東翼 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
序章 研究の対象と動向
第一部 モンゴル·高麗·日本に關連する新しい古文書資料
第一章 一二六九年「大蒙古國」中書省牒と日本側の対応
第二章 一三六六年高麗國征東行中書省の咨文についての検討
第二部 高麗人と元の文人との交游
第一章 新資料を通じてみた忠宣王の元での活動
第二章 李斉賢および権漢功、そして朱徳潤
第三部 日本遠征の指揮官——金方慶と洪茶丘、そして戦爭以后の麗·日關系
第一章 金方慶の生涯と行跡
第二章 モンゴルに投降した洪福源および茶丘の父子
第三章 十四世紀の高麗と日本の接觸と交流
終章 今后の課題
16、中國帰國者をめぐる包摂と排除の歴史社會學
時 間:2016年2月
作 者:南誠 著
出版單位:東京:明石書店
內容簡介:
序章 「中國帰國者」の境界文化
一 「中國帰國者」の問い
二 「中國帰國者」の先行研究
三 本研究の分析視角と枠組み
第一部 歴史編
第一章 國民の包摂と引揚
一 國民の送出と包摂
二 引揚と「再祖國化」
三 包摂の余剰
四 國民の包摂と外交
第二章 不完全な國民統合
一 法的處理と國籍問題
二 「殘余カテゴリー」の排除
三 法的主體の抹消
四 忘卻と記憶のあいだ
五 法の例外狀態
第三章 もう一つの包摂物語
一 実態の把握
二 日本人政策の模索
三 國籍と社會統合
四 剝き出しの生
第二部 表象/実踐編
第四章 忘卻と想起の痕跡
一 「日中友好手をつなぐ會」の活動
二 肉親捜し·帰國促進運動と日本社會
三 民間団體の主張
四 殘留と棄民の系譜
五 親密圏から公共圏へ
第五章 支配的物語の生成
一 記憶·表象するメディア
二 錯綜する記憶·表象
三 記憶·表象の政治學
四 「中國殘留日本人」は語られたか
第六章 境界の集合的構筑
一 「中國帰國者」の「再」包摂
二 國家賠償訴訟運動と社會的構筑
三 集合的表象
四 沈黙の語り
第七章 境界文化の政治學
一 命名のポリティクス
二 呼びかけられる行為體
三 境界文化の政治
四 境界文化の諸相
終章 生成的な境界文化
一 「中國帰國者」の歴史/社會的構筑
二 「よき國民」と社會的排除
三 今后の課題
17、アヘンと香港:1845-1943
時 間:2016年2月
作 者:古泉達矢 著
出版單位:東京:東京大學出版會
內容簡介:
序章 近代香港とアヘン問題
第1部 アヘン小売販売制度の誕生
第1章 征稅請負のはじまり
第2章 排華運動の影
第2部 國際體制からの挑戦
第3章 征稅請負制度から専売制度へ
第4章 連盟外交をめぐるジレンマ
第3部 専売制度の落陽
第5章 「密輸」をめぐる対立
第6章 澳門におけるアヘン問題
第7章 終焉への道程
終章 金の卵から疫病神へ
18、中國鎮魂演劇研究
時 間:2016年1月
作 者:田仲一成 著
出版單位:東京:東京大學出版會
內容簡介:
序章 中國演劇史における鎮魂演劇の地位
第一章 目連戲原本の探究――閩本
第二章 江南目連戲テキストの系統分化――古本·準古本·京本
第三章 郷村古層目連戲――古本I:贛本
第四章 郷村古層目連戲――古本II:徽本
第五章 郷村新層目連戲――準古本I:池本
第六章 郷村新層目連戲――準古本II:呉本
第七章 郷村新層目連戲――準古本III:浙本
第八章(上)宗族系目連戲――京本I:鄭本
第八章(下)宗族系目連戲の継受――京本II:湘本·川本
第九章(上)市場地目連戲の展開――花目連の挿演
第九章(下)市場目連戲の展開――連臺本の加演
第十章 目連戲の伝播と劇場演出――折子戲
結章 中國鎮魂演劇の體系
余論 宮廷劇『勧善金科』
19、中國議會100年史──誰が誰を代表してきたのか
時 間:2015年12月
作 者:深町英夫 編
出版單位:東京:東京大學出版會
內容簡介:
序章 誰が誰を代表するのか?いかに?(深町英夫)
第I部 中華民國前期
第1章 「選挙運動は不當だ!」──第1回選挙への批判(ジョシュア·ヒル)
第2章 「神圣」から「唾棄」へ──國會への期待と幻滅(王奇生)
第3章 民意に服さぬ代表──新國會の「議會専制」(金子肇)
第II部 中華民國后期
第4章 地域代表か?職能代表か?──國民黨の選挙制度(孫宏云)
第5章 一黨支配を掘り崩す民意──立法院と國民參政會(中村元哉)
第6章 権威主義的指導者と議會──蔣介石の自由民主観(汪朝光)
第III部 中華人民共和國初期
第7章 前衛黨と黨外勢力──建國期の「人民代表會議」(杜崎群杰)
第8章 実業界と政治參加──第1回全人大と中國民主建國會(水羽信男)
第9章 「國家の主人公」の創出──第1回人民代表普通選挙(張済順)
補論 民族/民主──國共両黨政権と満族の政治參加(深町英夫、張玉萍)
第IV部 現代
第10章 権威主義的「議會」の限界──地方選挙と民意(中岡まり)
第11章 人大に埋め込まれた機能――代理·諫言·代表(加茂具樹)
第12章 立憲主義か民主主義か?──中國大陸と臺灣(石塚迅)