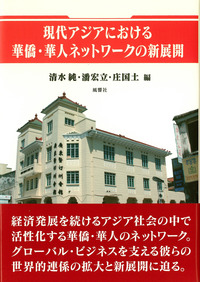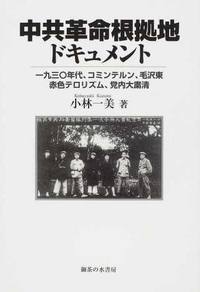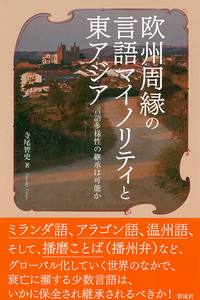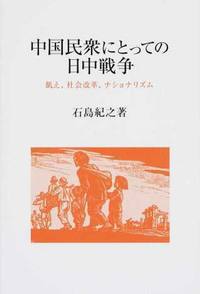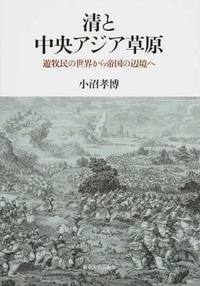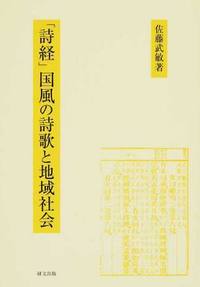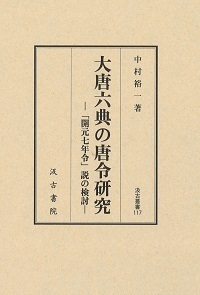日韓近期漢學(xué)出版物(九)
10、現(xiàn)代アジアにおける華僑·華人ネットワークの新展開
出版時(shí)間:2014年2月
作 者:清水純等 合編
出版單位:東京:風(fēng)響社
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
●第一部 グローバル化する華僑·華人ネットワークと華商ビジネス——その歴史的背景と現(xiàn)在
アジア東部の初期華人社団形成における主要な紐帯(莊國(guó)土〈石村明子訳〉)
家郷連系とビジネス·ネットワーク——清末民初における潮汕商人と故郷の相互關(guān)系(蔡志祥〈林松濤訳〉)
中國(guó)の華僑政策——一九五〇年代の試行と教訓(xùn)(曽根康雄)
香港·臺(tái)灣·東南アジア華人資本による中國(guó)への投資(崔晨)
臺(tái)灣と東南アジアを結(jié)ぶ華僑·華人の社団組織(清水純)
日本における新たな華僑組織と華僑(城田千枝子)
華僑の「クヮンシ」と社団の再生過(guò)程——同窓會(huì)ネットワークを中心に(李鎭榮)
インドシナ三國(guó)における華僑·華人社會(huì)の現(xiàn)狀(諏訪一幸)
マレーシアにおける中國(guó)新移民(廖大珂〈奈倉(cāng)京子訳〉)
●第二部 東南アジアにおける社団ネットワークの新たな動(dòng)向
中比國(guó)交樹立后のフィリピン華人社団の新たな変化および原籍地との關(guān)系——晉江籍社団を例として(莊國(guó)土·陳君〈玉置充子·石村明子訳〉)
シンガポールにおける中國(guó)新移民社団試論(劉文正〈林松濤訳〉)
一九八〇年代以降のタイ華人社団の新発展(潘少紅〈王艶梅訳〉)
ポスト·スハルト時(shí)代におけるインドネシア華人社団の新たな発展(丁麗興〈玉置充子訳〉)
一九八〇年代以降のマレーシア華人社団の新たな発展(鄭達(dá)〈玉置充子訳〉)
一九七〇年代中期以降のビルマ(ミャンマー)華人社団の発展と変化(陳丙先〈玉置充子訳〉)
一九八〇年代以降の東南アジアにおける泉州籍地縁型社団の変遷(林聯(lián)華〈殷娟訳〉)
一九八〇年代以降の広西籍の華人社団(梁炳猛〈高天亮訳〉)
11、中共革命根拠地ドキュメント
出版時(shí)間:2013年10月
作 者:小林一美 著
出版單位:東京:御茶の水書房
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
第一章 モスクワの中國(guó)人革命家·留學(xué)生とコミンテルン
第二章 「土地革命戦爭(zhēng)」の時(shí)代とその全般的情況
第三章 中央革命根拠地における毛沢東の「革命と粛清」
第四章 湘【カン】革命根拠地の大粛清
第五章 閩西革命根拠地の「社民黨」大粛清
第六章 鄂豫皖革命根拠地の大粛清
第七章 「湘鄂西根拠地」、「湘鄂【カン】根拠地」及びその他の根拠地の大粛清
第八章 『紅色中華』(中華ソヴィエト共和國(guó)機(jī)關(guān)紙)に見(jiàn)る「粛清反革命運(yùn)動(dòng)」
第九章 客家と「土地革命戦爭(zhēng)」
第十章 結(jié)論?同志が皆敵に見(jiàn)える時(shí)
12、東洋史研究第73卷第1號(hào)
出版時(shí)間:2014年6月
出版單位:京都:東洋史研究會(huì)
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
【論說(shuō)】
墓中の神坐——漢魏晉南北朝の墓室內(nèi)祭祀(向井佑介)
モンゴル時(shí)代の華北地域?會(huì)における命令文とその刻石の意義——ダーリタイ家の活動(dòng)とその投下領(lǐng)における全眞敎の事業(yè)(舩田善之)
明朝の國(guó)家祭祀と佛敎、道敎、諸神(淺井紀(jì))
中國(guó)共產(chǎn)黨による黨史編纂の歩み央朗——一九五〇年代の雜志『黨史資料』を手がかりに(石川禎浩)
【書評(píng)】
村上衛(wèi)著『?の近代中國(guó)史——福建人の活動(dòng)とイギリス·清朝』(藤原敬士)
13、白山中國(guó)學(xué)通卷20號(hào)
出版時(shí)間:2014年1月
出版單位:東京:白山中國(guó)學(xué)會(huì)
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
大塩平八郎の『儒門空虛聚語(yǔ)』論序說(shuō)(吉田公平)
近代精神と養(yǎng)気說(shuō)(上)(櫻井佑樹)
王畿『龍渓王先生會(huì)語(yǔ)』訳注:其の十六(吉田公平、小路口聡、早坂俊廣、鶴成久章、內(nèi)田健太)
中江藤樹編纂醫(yī)學(xué)書『捷徑醫(yī)筌』の依拠文獻(xiàn)(小山國(guó)三)
東アジアの“近代”という思想(有田和夫)
楊昌済の教育思想(土田秀明)
安徽省王畿講學(xué)關(guān)系地実地調(diào)査報(bào)告(伊香賀隆、播本崇史)
14、歐州周縁の言語(yǔ)マイノリティと東アジア:言語(yǔ)多様性の継承は可能か
出版時(shí)間:2014年7月
作 者:寺尾智史 著
出版單位:東京:彩流社
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
第一章 ミランダ語(yǔ)——「むくつけき田舎なまり」から「ポルトガル唯一の少數(shù)言語(yǔ)」へ
第二章 アラゴン語(yǔ)——王室のことばから谷底の俚言(パトワ)へ
第三章 少數(shù)言語(yǔ)保全と言語(yǔ)多様性保全との相克——アイデンティティ·ポリティクスの末路としての少數(shù)言語(yǔ)保全は言語(yǔ)多様性保全につながるか……
第四章 言語(yǔ)多様性は継承できるのか——東アジアからことばのグローバリズムを照らし返す“上海語(yǔ)”のふしぎや、溫州語(yǔ)のネットワークなどにも言及
第五章 液狀化社會(huì)における言語(yǔ)多様性継承の可能性——その多層的舞臺(tái)配置を母語(yǔ)環(huán)境から探る播州ことばなどにも言及
15、中國(guó)民眾にとっての日中戦爭(zhēng):饑え、社會(huì)改革、ナショナリズム
出版時(shí)間:2014年7月
作 者:石島紀(jì)之 著
出版單位:東京:研文出版
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
第一部 饑えとの戦い
戦場(chǎng)とその鄰接地域
浙江省——くりかえされる戦爭(zhēng)の被害/河南省―大饑饉
日本占領(lǐng)地域·汪精衛(wèi)政権支配地域―上海
上海戦の開始からアジア太平洋戦爭(zhēng)勃発まで/アジア太平洋戦爭(zhēng)勃発后
國(guó)民黨政府統(tǒng)治區(qū)——重慶と成都
共產(chǎn)黨支配下の抗日根拠地
民眾の負(fù)擔(dān)の増加/自然災(zāi)害との戦い
第二部 ナショナリズムと社會(huì)改革——太行根拠地の社會(huì)と民眾
村と農(nóng)民/太行地區(qū)の土地問(wèn)題
抗日根拠地の建設(shè)と民眾
抗日根拠地の建設(shè)/民眾運(yùn)動(dòng)の急進(jìn)化とその是正
抗日根拠地の危機(jī)
百団大戦と日本軍の反撃/晉冀魯豫辺區(qū)の成立/日本軍の治安強(qiáng)化運(yùn)動(dòng)と根拠地の縮小
危機(jī)の克服と根拠地の拡大
一九四二年の民眾運(yùn)動(dòng)/民眾運(yùn)動(dòng)の新たな展開/一九四四年から四五年の民眾運(yùn)動(dòng)
16、清と中央アジア草原:游牧民の世界から帝國(guó)の辺境へ
出版時(shí)間:2014年7月
作 者:小沼孝博 著
出版單位:東京:東京大學(xué)出版會(huì)
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
序論
第1部 清のジューンガル征服再考
第1章 游牧國(guó)家ジューンガルの形成と支配體制
第2章 清のジューンガル征服と支配構(gòu)想
第3章 オイラト支配の展開
第4章 オイラト支配の破綻
第5章 イリ軍営の形成
補(bǔ)論 清朝皇帝を指す満洲語(yǔ)
第2部 清の中央アジア政策と西北領(lǐng)域
第6章 清とカザフ游牧勢(shì)力の接觸
第7章 清の中央アジア政策の基層
第8章 清-カザフ關(guān)系の変容——1770年代の西北情勢(shì)
第9章 19世紀(jì)前半清の西北領(lǐng)域の再編
結(jié)論
17、「詩(shī)経」國(guó)風(fēng)の詩(shī)歌と地域社會(huì)
出版時(shí)間:2014年6月
作 者:佐藤武敏 著
出版單位:東京:研文出版
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
第一章 戀愛(ài)詩(shī)と地域社會(huì)
はじめに/鄭風(fēng)の戀愛(ài)詩(shī)/衛(wèi)風(fēng)の戀愛(ài)詩(shī)/鄭風(fēng)·衛(wèi)風(fēng)戀愛(ài)詩(shī)の特色/戀愛(ài)詩(shī)と鄭·衛(wèi)の地域社會(huì)/陳風(fēng)の戀愛(ài)詩(shī)とその特色/戀愛(ài)詩(shī)と陳の地域社會(huì)/附 中國(guó)古代の俗楽―鄭聲を中心に
第二章 魏風(fēng)に見(jiàn)える生活苦の詩(shī)と地域社會(huì)
魏風(fēng)に見(jiàn)える生活苦の詩(shī)/魏風(fēng)の地域社會(huì)
第三章 秦風(fēng)に見(jiàn)える車馬の詩(shī)と地域社會(huì)
秦風(fēng)に見(jiàn)える車馬の詩(shī)/秦風(fēng)の地域社會(huì)
第四章 豳風(fēng)(ひんぷう)に見(jiàn)える農(nóng)事詩(shī)と市域社會(huì)
はじめに/頌·雅の農(nóng)事詩(shī)/頌·雅の農(nóng)事詩(shī)の地域社會(huì)/豳風(fēng)七月の詩(shī)/豳風(fēng)の地域社會(huì)
18、大唐六典の唐令研究:「開元七年令」說(shuō)の検討
出版時(shí)間:2014年6月
作 者:中村裕一 著
出版單位:東京:汲古書院
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
従來(lái)、『大唐六典』所載の唐令は「開元七年令」とされてきた。それは『唐令拾遺』が「開元七年令」と斷定したことによる。「開元七年令」說(shuō)が提出されたのは一九三〇年代のことであり、爾來(lái)、この說(shuō)に異議異論を唱えた者はない。私もこの通說(shuō)を信じた一人で、二〇一一年六月に『中國(guó)古代の年中行事』(汲古書院)全四冊(cè)を校了にするまで、『大唐六典』唐令=「開元七年令」說(shuō)には重大な誤りがあるとは思い及ばなかった。『中國(guó)古代の年中行事』を書くにあたっては、年中行事と關(guān)連が深い「祠令」にも關(guān)心をもちい、『大唐六典』巻四尚書禮部·祠部郎中員外郎職の條に記載される唐代の「祠令」と、その關(guān)系史料に注意をはらった。祠部郎中員外郎職の條には「斉太公」に關(guān)する「祠令」がある。「斉太公」の祭祀は開元一九年(七三一)から開始されたと、『舊唐書』をはじめとする唐代史書は明記する。果たしてそうであれば、「斉太公」に關(guān)する「祠令」は、開元七年「祠令」には存在しないことになる。
『大唐六典』の細(xì)字の注記に記載される開元二〇年代の改訂官品(増品官品と降品官品)が、『大唐六典』本文の官品と『通典』巻四〇職官典の開元二五年官品と、極めてよく一致する事実を見(jiàn)いだした。
開元二〇年代に改訂された官品であるから、この改訂された官品は開元七年官品ではなく、この官品は、開元二五年官品であろうと考えるに至った。さらに改訂官品だけが開元二五年官品ではなく、『大唐六典』の本文に記載される官品すべては、開元二五年官品と考えるに至った。官品だけ開元二五年「官品令」に依り、『大唐六典』の他の「令」は「開元七年令」であるはずがない。官品に加えて定員を検討した。
これも『通典』職官典に記載する開元二五年の定員と一致する。それも開元七年以降の改訂された定員とである。改訂定員は開元七年の定員ではなく、これが『通典』職官典に記載する開元二五年の定員と一致するから、『大唐六典』の本文に記載する定員は、開元二五年「職員令」ということになる。「官品令」と「職員令」だけが「開元二五年令」で、他の「令」が「開元七年令」というのも、実に奇妙である。
『大唐六典』の細(xì)字注記に「舊令」という語(yǔ)が四回出てくる。例えば、『大唐六典』巻八門下省·主事に「四人、従八品下」とあり、注記に「舊令」の語(yǔ)がみえる。「晉置門下主事、歴宋斉、品第八。梁陳名為門下主事令史。北斉門下主事令史八人、従第八品上。隋初、諸臺(tái)省并置主事令史。煬帝三年、直曰主事。舊令、従九品上。開元二十四年勅、加入八品。」門下省の主事は「舊令」では従九品上の官品であったが、開元二四年の勅書によって一階進(jìn)められて従八品下となった。開元二四年以前の「官品令」を「舊令」というのであるから、「舊令」は開元七年「官品令」を指すことになる。これによって『大唐六典』は「開元七年令」を述べた書ではないことは明らかで、『大唐六典』の唐令は「開元二五年令」なのである。「開元七年令」說(shuō)は大いる誤解から派生した虛構(gòu)の產(chǎn)物であり、到底成立しない說(shuō)である